近所のマスターがテレビに出ていてちょっと嬉しい

こんにちは。imoimoです。
てきとーな製作をやっております。
新品のノートPCをゲットしたので、折角だからタダで製作環境を調えて行く記録をしております。
これまでで
- 基本的なツールを入れて
- DAWを入れて
- ベーシックなFXを入れて
- 一通り使いそうな音源を入れて
- シンセを入れました。
それにしても。
どうやって
曲を作って行くのが普通なのだろう。
なにしろタダ前提なんで、オーディオインターフェースも使いません。
これ、て「弾かない」前提て事だよねと思います。
とすると、大抵は何か1トラック打ち込みとかで作って肉付けして行くのが普通かしら。
- ピアノか何かのトラックを作って、そこにベースやらドラムを付けるとか。
- ギターのリフを作って、ベースとドラムを付けるとか。
- いやいや。先にドラムを鳴らしておいてベースを作るとか。
…まあ何でも良いのですが、問題はCPUのリソース。
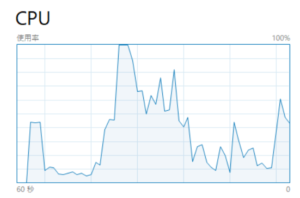
プラグインの音源は、結構リソースを使います。
自分だけかと思っていたけど、そこら辺のPCでオーディオインターフェースも使わない場合はだいたい6、7トラック辺りから苦しそうになるみたい。
オーディオインターフェースを使ってDSPを外付すればもっと凄いのか??と思うのですが。

多かれ少なかれ苦労はあるみたい。そんなんなら買わなーぃっ。
正しくは「買えない」です。
そんなわけだから、トラックは順次オーディオに書き出しながら作る方が得策だと思います。
オーディオに書き出すと言うのは要するに録音する様なもので、やり直しもカンタン。
世間ではこの作業をレンダリングと言う様です。
レコーディングじゃないのね。
バウンスと呼ぶ時もあるけれど、バウンスと言うのは複数トラックをまとめる時の方が多いみたい。
ミックスダウンじゃないんだ。
いずれにしても。
弾いたり歌ったりしないで曲を作る時には音源を鳴らして、一旦オーディオに録り直す必要があります。
録ったオーディオトラックでは、手直しする必要がよくあるわけでして。
トラック単体で音を整えたり、弦なら弦管なら管で複数をひとまとめにしたり。
バストラックと言う様です。
例えばバイオリンAさんとBさんの二人を仲良くまとめたい時とかに、二人を仲良しにさせる魔法みたいなプラグインがあったり。
最後の最後に全体に使うプラグインがあったりします。
こう言うプラグイン類をバスなんちゃらとかマスターなんちゃらとかよく呼んでおりますが、難点がいくつかあって。
- 難しい
- 大抵有料でバカ高い
- 動作が重い
- 効果は微妙でよくわからない
要するに大人向け、て事。
そんなわけで「おとなプラグイン」としました。
タダで、こどもにも扱えるおとなプラグインをまとめておきます。
コンプレッサー
普段使うのはReaCompなんだけど(→ダウンロード)。

おとなコンプはちょっとムードが違って。でもこどもにも優しいのは例えば
MJUC Jr.

もうね。見た目からしてお・と・な。
グルー効果が気持ち良いと言われるバスコンプです(→ダウンロード)。
結構CPUパワーを使うからあっちゃこっちゃに挿すと大変です。
例えばバイオリンAさんとBさんとセロをまとめたバスに挿すと。
何が変わったんだかさっぱりわからないけれど、自然とみんなが調和した音になります。
同じコンプレッサーとは思えない感じ。
他には
DCAM Free Comp

実機の卓のコンプをモデリングしたそうで。MJUC Jr.と比べると、もうちょっと「かかってます」風味の強いバスコンプ(→ダウンロード)。
マシンがすんごい高性能ならトラックに使っても良いかもね。
モデリングと言うだけあって、実機のミキサーっぽいかかり方な気がします。
こんな感じに、おとなプラグインは「○○モデリング」と言うものが多い様です。
だいたいがアナログ回路の実機を再現している感じかしら。
有名な実機になるとお値段も実機並みかも。
先日一瞬マイブームだったのは
Kompreskimo
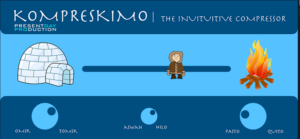
エスキモーがノリノリで踊るコンプレッサーです(→ダウンロード)。
ジョークグッズなのかと思ったけれど、かかりは結構気持ち良いのよ。
リズムトラックとかに使ってみました。
マキシマイザー
別におとなじゃないじゃん、と言われそうですが。
閾値よりも低いレベルを増幅するエクスパンダ―と、閾値よりも高いレベルを抑えるコンプレッサーを組み合わせるとマキシマイザーになると言うのが基本原理みたい。
要するに音が目の前に寄って来る様な聴こえ方になって。
目の前でギャンギャンやっている様な状態になるから、音圧が上がると言う事の様です。
単純に音がデカくなるから、こどもにとってはサイコー。
と言うわけで何でもかんでも挿したくなるのが
W1 Limiter

すんごく有名な無料のリミッター/マキシマイザーです(→ダウンロード)。
全トラックにこれ挿す人がいるくらいに中毒性があります。
でも動作は物凄く上品でクリア。
ちゃんと使うべきところに使ってね、と開発者のGeorge Yohngさんに言われそうです。
めちゃめちゃいい人そう…
なるべくマキシマイザーに頼らない曲作りをしたいものです。
でも最後のマスターでは音圧調整に使いたいのですが、そうなるとこっちの方が好みだったりして。
Unlimited

5.1chに対応したリミッター/マキシマイザーです(→【Plugins4Free.com】)。
この辺りから、メーターが無いとワケ分からない感じになるので
スペクトラムアナライザー
見たってわかりゃしませんが。何となくね。
他にはトゥルーピークとかRMSとか株価診断みたいな数値が色々と表示されるので、何となく。
タダのものだとVoxengoのが良いと思います。
SPAN

Blue Cat AudioのFreePackにもスペアナは入っていますが、
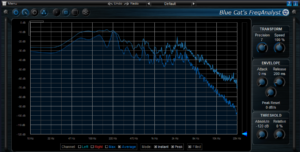
こっちの方が見やすい気がします(→ダウンロード)。
どっちにしても、スペアナは負荷が大きくて表示落ちする事がしょっちゅう。
今度のノートPCはグラボ積んでるから改善されるかしら…
そう言えば
Voxengoのプラグインにも無料のものは結構あって(→【voxengo.com】)。
そもそもVoxengo自体がおとなデベロッパーな気もします。
ちょっと難度の高いプラグインが多いのよ。
Mid/Sideエンコーダー/デコーダーのMSEDとか。
使ってるとカッコつけになるかも知れません。
…おとなプラグインは思ったよりあるな。続きは明日にしよう。
そんなこんなでお粗末様でした。






コメント